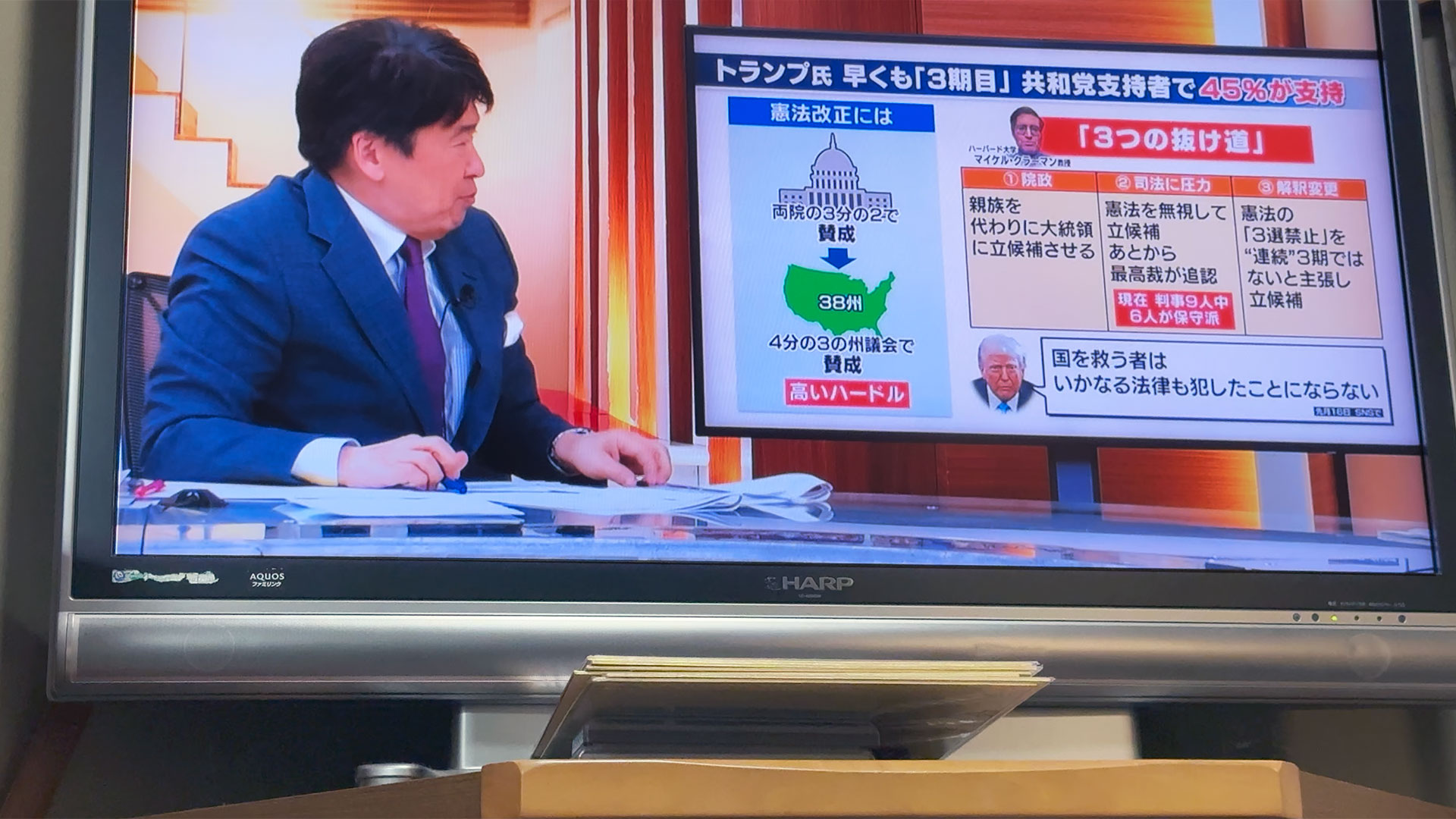「陸上競技を科学する」を聴講して
スポーツ科学と医療の融合による競技力向上への提言
本日、名古屋大学陸上競技部主催の講演会に参加いたしました。
名古屋大学保健体育センター教授の講義を聴講し、競技力向上にはスポーツを科学し、実践することが重要であるという認識を深めました。
例えば、やり投げの選手において、立ち投げ(走らないで投げる)で成績が優れた選手ほど、本番の競技でも槍を遠くへ飛ばすことができると考えられますが、実際に被験者を対象としたデータ収集の結果、必ずしもそうではないとのことです。
そこで、助走の最終速度の速い選手ほど、遠くへ飛ばすことができるのかという疑問が生じますが、必ずしもそうではないようです。槍をリリースする前の加速開始時点での手足の動き、例えば上腕の外旋、水平外転等の動きの中で、筋肉の弾性要素が十分生かされているかどうかが重要なポイントであり、このような仕組みを検証する必要があります。
しかしながら、検証結果で得られた仕組みを理解できれば、立ち投げの苦手な選手や助走速度の遅い選手であっても、適切なフォームを習得することで競技成績を向上させることができると考えられます。
ハンマー投げにおいては、体重と記録に相関関係が認められるため、体重を増やすことが必要であるとされています。
ハンマーを持って身体を回転させると、ハンマーヘッドは同様に円運動し、遠心力が加わります。これに逆らってハンマーを引くことで、さらに遠心力が高まります。そして、回転の軌道面を徐々に傾け、45度に近い角度でリリースすると、より遠くへ飛ばすことができるという仕組みを理解することはもちろん重要ですが、体重を増やすことがハンマー投げの競技力を高めることが科学的に明らかになっているのであれば、ハンマー投げ選手には、技術的要素に加えてウェイトトレーニングを取り入れていく必要があるでしょう。
以上のように、スポーツを科学することは、競技力向上方法を明確に示してくれるという点で意義深いものです。
しかしながら、私が危惧するのは、「スポーツを科学する」という考え方の中に、スポーツ外傷・障害への配慮が十分に行われていないのではないかということ。
人間は生身の身体であるため、スポーツ外傷・障害も視野に入れて考える必要があります。
例えば、タータントラックが望ましい練習環境であるというお話がありましたが、タータントラックは走路が堅く、足腰への負荷を増大させる可能性も考えられます。
長距離走選手がスピードを向上させるためのトレーニングやインターバルトレーニングを繰り返し実践する場合、下腿、大腿、腰臀部周辺の筋力が不足していれば、脛骨過労性骨膜炎、膝痛、腰痛、下腿疲労骨折、足部疲労骨折などの故障が発生する可能性が高くなるのではないでしょうか。
私は整形外科の診療所に勤務しており、アキレス腱炎をはじめとする多くの怪我で苦しむスポーツ選手に接しているので、このことを切実に感じています。
雨天時でも練習できることや、スピードを向上させる効果的なトレーニングができること、タータン舗装であることなどをメリットと考えるのは早計であると考えます。
一度怪我をしてしまうと、競技に復帰するまでには相当な時間を要します。それは、雨天時における練習時間の損失を大きく上回るものです。
私が以前勤務していた「スポーツ医・科学研究所」は、スポーツを科学する研究員とスポーツ医学を専門とする医療従事者が互いに意見交換を行いながら、日本のスポーツの発展に寄与することを目的として設立されました。
しかし、同じ屋根の下で、開所当初こそ互いに意見交換を行いながら共同で業務を行っていましたが、研究員は研究員の領域があり、医療現場では患者の治療や業務に追われる日々が続き、会議を開いて意見交換する場が次第に少なくなっていきました。気が付けば、互いに専門分野としてそれぞれが別部門として独立して業務を行っているような状況でした。
日本のスポーツ選手の競技能力を高めるためには、スポーツを科学する科学者とスポーツ外傷・障害に携わる医療従事者が互いに意見交換を行いながら、最良のトレーニング方法を考案していくことが望ましいと考えます。
投稿:2006年11月25日
安藤秀樹
フジミックスTV